
【受付終了】10月19日(日)山梨県・フルーツグロアー澤登に...
2025.9.5

2025年10月19日、山梨県牧丘町にあるフルーツグロアー澤登(さわのぼり)で、「有機ぶどうの収穫&ジャムづくり体験」を開催しました。

「ぶどうに囲まれて育った。」そう語るのは、澤登早苗さん(写真右)。
1950年代に先代の芳さんがぶどう栽培を牧丘町の地に定着させ、1970年代には、当時はまだ難しいと言われていた国産ぶどうの有機栽培を成功させました。その志を、夫の芳英さん(写真左)とともにつないでいます。現在、フルーツグロアー澤登では、様々な品種の有機ぶどうと有機キウイフルーツを栽培しています。

ぶどう畑には、森の入り口のようなアーチをくぐって入ります。ふかふかの土を踏みしめて進むと、ちょうど大人の顔の高さにぶどうがたくさんなっています。子どもたちも、目を輝かせて見上げています。
今回収穫するぶどうは、「ワイングランド」。そのまま食べるほか、ワインやジュース、スムージー、デザートにも適した品種です。

地面には下草がたくさん生えています。実は、この下草は、土の通気性や保水性を高める役割を果たしています。刈ったあとは、置いておくと分解されて土に戻り、農園の地力を維持することにつながります。
また、ぶどうを守ってくれる天敵昆虫のすみかになり、多様な虫たちが生息することで害虫化しなくなります。そのため、農薬を使わない有機栽培においては、積極的に下草を生やすそうです。下草は、ぶどうの健康な生育を支える大切な要素だったのですね。
美味しそうな房を探し、「見つけた見つけた!良いやつ!」と、房の根元にハサミを入れます。


もぎたてのぶどうを口に入れると、その柔らかさに驚きます。
欧州系のぶどうはパリッと皮を噛むと果汁が弾けるような食感ですが、それに対して日本のヤマブドウを親に持つ品種であるワイングランドは、果肉が柔らかく多汁です。口の中で、じわ~っと深みのある優しい甘さが広がります。完熟なので、皮ごと口に入れ、種まで噛んで食べられます。
「柔らかいので、一気に口に入れても詰まらないのよ」と早苗さん。「息子が小さい頃は口いっぱいにぶどうを頬張ってました」と笑顔で話されていました。

畑を見渡すと、時々、シワシワの房があります。これは天然の干しぶどうで、食べても大丈夫。果汁がぎゅっと濃縮され、濃厚な甘みです。出荷の際はシワシワの粒は1つ1つ手作業で取り除かれるので、もぎたてでしか味わえません。

収穫中は雨が降っていましたが、屋根があったので快適に過ごせました。実はこの屋根も、ぶどうの有機栽培においてとても重要な役割を果たしています。
ぶどうは本来、カラッと乾いた気候を好みますが、日本は湿気も雨も多いです。つまり、ぶどうが好む気候と日本の気候は正反対。農薬なしでは病気やカビが起きやすいのです。これが、日本でぶどうの有機栽培が極めて難しいとされる理由です。
慣行農業では、雨が降った後、病気の発生を抑えるため農薬を散布します。フルーツグロアー澤登では、その代わりに「サイドレスハウス」と呼ばれる側面を覆わない屋根が設置され、これによって雨を除けるとともに、通気性を確保し、湿気を逃がす工夫をしています。屋根のビニールの張り替えは、現在は息子の芳秋さんが担当。風が吹いて揺れるので、慎重に作業をする必要があるそう。
サイドレスハウスは、農薬を大量に使う慣行農業に対して危機意識を抱いた先代の芳さんによって開発されました。開発には約7年の歳月を要し、特許も取得されています。
フルーツグロアー澤登では、1970年代から農薬を一切使わず有機ぶどうを栽培していますが、その技術の確立にはサイドレスハウスが大きく貢献したのです。

箱いっぱいにぶどうを詰めて、収穫完了。

中にはクモの巣がかかっている房もありますが、実はクモはぶどうの味方。ぶどうを食べにくる虫を食べてくれるのです。クモは農薬に敏感で、撒くとすぐにいなくなってしまうそうです。クモがいるということは、安心して食べられる証とも言えますね。
しかし、やはり出荷するときはそのままにはしておけません。クモやクモの巣はピンセットで丁寧に取り除いていくそうで、この作業が最も大変だと仰っていました。

雨が弱まってきたので、畑の周辺を散策しながらジャムづくりの会場となる公民館へと向かいました。

牧丘町を含む山梨県の峡東地区は、世界農業遺産に認定されています。
世界農業遺産の認定には、自然や地域の文化と調和した農業の営みが求められます。地域の伝統とともに農業を長く続け、人々の生活を支えると同時に美しい景色をつくっていく必要があるのです。
フルーツグロアー澤登の周辺は、標高650メートルに位置し、晴れた日には富士山が綺麗に見えるそうです。この日はあいにくのお天気でしたが、それでも一面に広がるぶどう畑は圧巻。思わず深呼吸したくなる景色です。

「ぶどうをたくさん食べたから、おなかをすかせなきゃ。」
参加者一同、早苗さんに続いて歩いていきます。周辺は「巨峰の丘マラソン」のコースにも指定されているそう。木の実や草花に目を向けながらゆっくりと進み、途中で野生の山椒をかじってみたり、水路を流れる冷たい水にさわってみたりしました。
散策中、ほかのぶどう園を多く通りがかりました。フルーツグロアー澤登の周辺は、全体的に農薬の使用量が少ないエリアですが、やはり慣行のぶどう園では農薬を使います。
有機栽培では、隣接する慣行農園からの農薬や化学肥料の飛散・流入の危険がある場合、何らかの防護措置をとる必要があります。きちんと措置がとられた農産物にだけ、有機JASマークをつけることができる決まりになっています。
フルーツグロアー澤登の周辺のぶどう園には、許可を得て農薬の飛散防止のために澤登さんがカーテンを設置しています。周囲の協力があって、初めて有機栽培ができるのですね。
30分ほど歩いてゴールの公民館が見えてくると、子どもたちが「はらへった!」と駆け出しました。たくさん歩いておなかをすかせよう作戦、無事成功です。

公民館でお弁当を食べたあと、澤登ご夫妻から「ぶどうの一年」についてお話を伺いました。普段は大学の教授もされているお2人。教壇に立つ姿を想像できる時間でした。
ぶどうの成長の様子を写真で見ていくと、まずは花の小ささに驚きました。収穫後の立派な実からは想像できないほどの豆粒サイズ。その小さな花からできた小さな実が、7~8月にかけて一気に膨らむ様子を見ることができました。
季節に合わせて変化する畑周辺の景色や、畑を訪れる生きものも合わせてご紹介いただき、自然の中で育つぶどうの様子を知る機会になりました。作物がどう育つのかを知ると、これまで以上に「いただきます」に気持ちがこもります。
そして、いよいよジャムづくりです。

収穫したぶどうをサッと水で流して汚れを落としたら、実を鍋に入れて火にかけます。有機だから、ごしごし洗わなくても大丈夫。つまみ食いしたくなる気持ちをぐっと堪え、鍋を見守ります。
パチパチと音が鳴りだしたら、マッシャーで実を潰し、ざるに移してジュースを搾ります。

次に、ジュースを搾った残りかすをもう一度鍋に入れ、さらに火にかけてジャムにしていきます。部屋中に甘い香りが漂い、さっきお弁当を食べたのにもう腹ペコです。

まずは絞ったジュースで乾杯。一口飲むと「甘っ!」と驚きの声があちこちで上がりました。

そして、出来上がったぶどうジャムを、ビオ・マルシェの食パンに乗せていただきました。ジャムは、なんと種入りです。柔らかい実と皮に、カリカリの種が良いアクセントになっています。
今回、ジュースもジャムも砂糖を加えていませんが、どちらもぶどうの甘みだけでとっても美味しく仕上がりました。
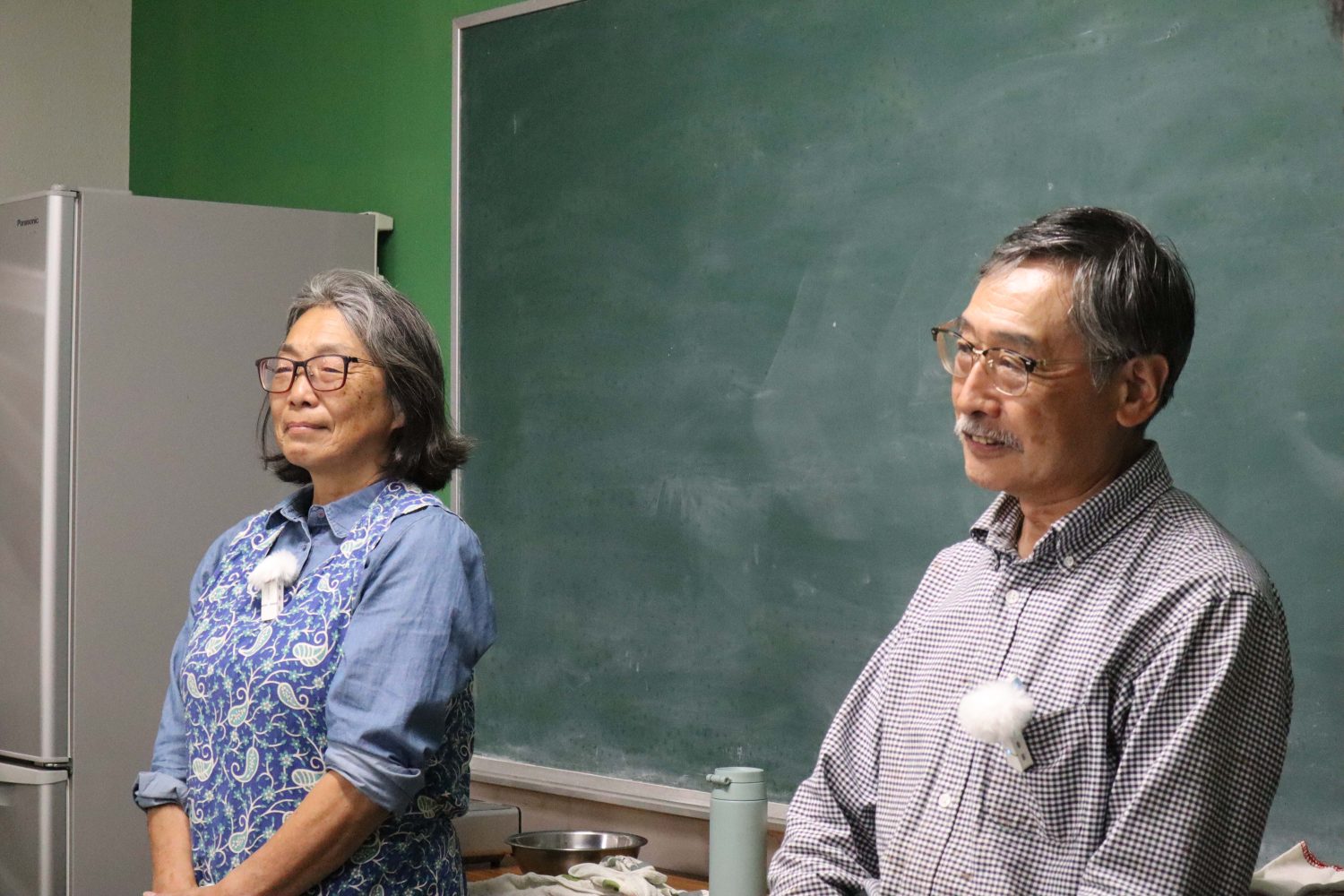
澤登ご夫妻は、「長く続けられる農業」を大切にしておられます。
農薬の害を一番受けるのは、生産者。農薬が原因で体調を崩し、栽培をやめてしまう人が多くいるのだそうです。その点、慣行農業は命がけです。農薬を一切使わない有機栽培にこだわる理由は、その持続可能性にあったのですね。
安心して食べてもらえる美味しいぶどうをずっとつくり続けられるように、ご夫妻は難易度の高いぶどうの有機栽培にこれからも挑戦されます。ビオ・マルシェの宅配は、できたぶどうをお客様にお届けすることで、これからもご夫妻の有機栽培への挑戦を応援していきます。
ご夫妻の努力と工夫と愛情の結晶ともいえる有機ぶどう。皆さんもぜひ食べてみてください。

参加者の皆さまより、心温まるメッセージを多数いただきました。
お寄せいただいたご感想は、澤登さんやスタッフ一同でありがたく拝読しました。
蜘蛛がぶどうを守ってくれていたとは、新しい学びでした!
今回は、果樹園にお邪魔させていただき、ありがとうございました。
有機栽培の実際の様子を見ることができて、とても貴重な体験となりました。蜘蛛がぶどうを守ってくれていたとは、想像もしておらず新しい学びでした!草も虫たちも役割があって、共生して育まれた命をいただいているという実感が湧きました。これからも家族や大切な人の身体に入るものとして選び続けていきたいと思います。ずっと、応援しています。(I様)
お砂糖を使っていないジャムが、こんなに甘くなるなんて。
初めは、クモの巣が張っていたり枯れているぶどうが有ったり…今まで行ったことの有るぶどう園との違いに、正直、不安でした。しかし、一口味見をしてみると、あまりの爽やかな甘さに驚きました。天然の干しぶどうになっていた部分は、貴腐ワインの様な味で、私はこちらの方が好きかもしれません。両方共、とても美味しくいただく事が出来ました。ジャムは、お砂糖を使っていないのに、こんなに甘くなるのか…と感心しました。お土産のぶどうで家でも作ってみようと思います。(T様)
ただのぶどう狩りでおわりではないところがいい。
子どもがいる家庭としては、ビオ・マルシェの収穫体験は素敵な食育企画だといつも思っています。ただのぶどう狩りでおわりではないと言うところがいいなと思っています。生産者の思いがつまっている野菜や果物をこれからもありがたく頂いていきたいと思います。(A様)

フルーツグロアー澤登(左:芳英さん、右:早苗さん)
澤登 芳英さん 共同代表
宇都宮大学大学院修士課程修了後、東京農工大学大学院連合農学研究科博士課程へ進学。農学博士号を取得。その後、林政総合調査研究所に研究員として勤務。2014年から家業の有機農業に取り組む。現在は、東京農業大学・山梨県立大学で非常勤講師も勤める。
澤登 早苗さん 共同代表
東京農工大学卒業、同大大学院在学中にニュージーランド留学、同大大学院連合農学研究科修了(農学博士)。1994~2024年まで恵泉女学園大学教員、現在恵泉女学園大学名誉教授。大学で有機園芸による教育実践をしながら父・澤登芳が開発した
農薬・化学肥料を使用しないブドウとキウイフルーツの栽培を継承、日本の有機果樹栽培の第一人者として活躍されています。