
【イベントレポート】柔らかさと甘さに驚き!種まで美味しいフル...
2025.11.12

有機JAS認証を取得した有機野菜のお届けにこだわってきたビオ・マルシェの宅配では、一般的に害虫や病気などの被害を受けやすく、有機農法での栽培が難しいとされている果物についても、一部有機JAS認証を取得したものを取り扱っています。
今回、有機の果物の中でも特に希少な有機いちごを栽培している、かみむら農園の上村さんの畑で、収穫体験イベントを開催しました。

上村さんの有機いちご畑は京都府の南に位置する八幡市にあります。一帯は木津川南岸に広がる田園地帯で、近くには時代劇などのロケでよく使われることで有名な「流れ橋(上津屋橋)」があります。
京都府南部では近年いちご栽培が盛んです。畑に向かう途中にも「いちご狩り」と書かれたのぼりが立っている観光農園がいくつか目に入りました。

田園地帯を碁盤の目のように走る細い農道を進んだ先に、上村さんのかみむら農園のハウスがあります。

上村さんが農業においてこだわっているのは作物の「おいしさ」。
おいしいものを作って、子どもたちが「おいしい!」と食べてくれる姿を見たいから、子どもたちが喜んで食べてくれるようなおいしい野菜や果物を作ることが、農家である自分の責任だと上村さんは語ります。

上村さんにハウス内での注意事項をご説明いただいた後、いよいよ収穫体験スタート。当日は4月上旬でしたが、天候に恵まれ、ハウス内の気温は27度。汗ばむくらいの暑さでした。


上村さんの有機いちご畑は、いちご栽培で一般的に見られる「高設栽培」(地面から一定の高さに苗床を設置し、そこで作物を栽培する方法)ではなく、ハウス内の畝に直接植え付けがされています。
有機JASの基準では土壌を利用した栽培を基本としているため、土づくりがとても大切です。
上村さんは「美味しいもの、自然由来のものを与えた作物は美味しい。」という考えのもと、基本的に植物性の肥料を使うことにこだわっています。例えば、豆腐屋さんからいただいたおからと米ぬかに、乳酸菌と酵母菌を加えて発酵させた自家製堆肥を使っています。
また、できる限り地元のものを使って、地域の中で農業をやっていきたいという想いも持っています。例えば、近隣の京都府・山城地域で伐採された青竹を使った竹パウダー。これは青竹を粉砕し、パウダー状にしたものを1~2か月置いておいたものです。青竹が持つ乳酸菌によって発酵が進み、堆肥になるのです。
ハウスの中では小さな虫も飛び回っています。虫の正体は実は「ハエ」。

このハエは「ビーフライ」といって、清潔な環境で育成・管理されている農業用のハエで、衛生面の問題はありません。彼らはミツバチなどの蜂に代わって、いちごの受粉をしてくれます。蜂のように、刺されてアナフィラキシーショック(重篤なアレルギー反応)を起こす心配がないため、農家さんも安心して作業できます。さらに、奇形果と呼ばれるいびつな形のいちごが発生する確率も低いとのこと。普段は嫌われ者のハエですが、いちご畑にいると少しだけ可愛く見えるのは不思議です。ちなみにビーフライは1匹あたり4円するそうで、ハエをそのような視点で見るのもまた新鮮な経験でした。


ご参加いただいた会員様やご家族の方々も、畝の間を巡りながら、赤く実ったいちごを探します。
子どもも大人も、おいしそうないちごを見つけては大喜びしていました。

上村さんが目指す理想の味は、「口の中に長く余韻が残り続ける単調でない味」。
甘いだけ、酸っぱいだけ、の単調な味覚は口から一瞬で消えてしまいますが、甘さと酸っぱさが絶妙なバランスで絡み合うと、香りやコクが生まれて、味の感覚がらせん状に増えていき、おいしさが口の中に長く残り続けるそうです。
参加された皆さんの「甘い!」「おいしい!」と驚きの声が、畑のあちこちから聞こえていました。


有機いちごのおいしさを堪能した後は、上村さんから栽培についての貴重なお話を聞かせていただきました。
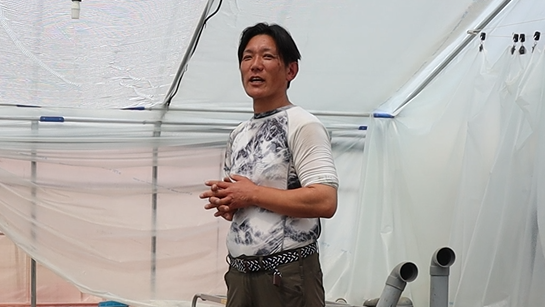
上村さんが農業を始めたのは2005年頃。お義父さんが家庭菜園で育てたナスのおいしさに感動したのがきっかけだったそうです。
そして、本格的に農業を学ぶために京都の有機農業の先駆者であった師匠と出会います。
そこで師匠から袋いっぱいのピーマンをもらうのですが、上村さんはピーマンがあまり好きではありませんでした。「こんなにたくさんのピーマンどうすんねん」そう途方に暮れながら、食卓に出てきた師匠のピーマンを食べると、「この世のものとは思えないおいしさだった」そう。それで、こんなおいしいピーマンを作る人の農業はおもしろそう、と、有機農業を学ぶことにしたそうです。
有機いちごを栽培する農家は国内に数えるほど。日本国内で生産されている有機いちごの量について正確なデータはありませんが、上村さんの見立てでは、わかりやすくパック数で表すと、50,000分の1パックくらいの割合(0.002%)でしかないのではないかとのことでした。
これはひとえにいちごが害虫や病気に非常に弱い作物のため。慣行栽培であれば比較的簡単に害虫や病気の発生を抑えることができますが、有機栽培ではなかなかそのようにはいきません。
このような話を聞くと、「有機のいちごは無農薬で栽培しているから大変なんだな」と思われる方もいるかもしれません。この点について、上村さんにお伺いすると、驚くようなセリフが。
「実は今も農薬散布中なんですよ」
「えっ?」と驚く皆さんに上村さんが見せてくれたのは、1本のボトルでした。

これはククメリスカブリダニ剤といって、ダニ、アブラムシ、アザミウマを食べてくれる「カブリダニ」という虫が入っています。化学合成された薬剤ではなく、微生物や昆虫などの生き物を有効成分として利用する農業用資材(いわゆる生物農薬)の一種です。
有機栽培なのに無農薬じゃないの?と思う方もいるかも知れません。
実は有機JAS法では、農産物に重大な損害が生ずる危険が迫っているが、他の方法(耕種的防除、物理的防除、生物的防除又はこれらを適切に組み合わせた方法)では防ぐことができない場合には、天然由来の成分を基本として、環境や生態系への影響が少ない農薬の使用が認められています。
耕種的防除 適切な作付け計画や、耐病性品種の利用
物理的防除 防虫ネットやトラップの使用
生物的防除 害虫の天敵である微生物や昆虫などの利用
農薬と聞くと、殺虫剤、除草剤などの薬剤を思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし、日本には農薬取締法という法律があり、作物に対して何らかの作用を目的として使用するものは、すべて農薬として登録が必要となるため、先ほどのククメリスカブリダニ剤も法律上の扱いは農薬となります。もちろん有機JAS法上で使用が認められており、比較的安全性が高い資材です。
いちご栽培では、他にも害虫対策に「納豆菌」が使用されることもありますし、もっと身近なものでは「お酢」も病害虫の防除を目的として畑に撒けば、農薬なのです。
もちろん、有機JAS法上認められた農薬でも、全く使用せずに栽培されるケースもありますが、「(有機農業の価値を)無農薬というくくりだけで見てしまうと農家がガチガチに固められる」と上村さんはおっしゃいます。
上村さんは、消費者に求められる「無農薬」にこだわって、有機JAS法上認められた農薬さえも全く使わなかった結果、失敗してしまう農家さんをたくさん見てこられたそうです。
そしてご自身も、かつて畑でうどん粉病が発生した時、経験不足もあって、何も手を打つことができずに1週間で畑が全滅してしまうという苦い経験をされたことがあったそう。
上村さんが、「有機農業に取り組む農家さんが増えて育っていくためにも、そういう苦労もあるということを知っておいてほしい」とおっしゃっていたのが印象的でした。
イベントの終わりに、希望者の方にいちごの特別販売を行いました。
いちごのパッケージには「瑠璃の宝箱」と印刷されています。

この名称の由来についても教えていただきました。
いちごを初めて植えたのは2016年。当時はまだ小学校低学年だった娘さんに食べさせたい、という気持ちから、いちご栽培を始めたそうです。
「瑠璃」というのは、実は娘さんの名前。いちごが採れ始めた頃は1日の収穫は2~3粒で、そのわずかないちごを取られまいと大事そうに食べる姿が「まるで宝箱を大事にかかえているようだった」から、「瑠璃の宝箱」と名づけたとか。
そんな娘さんは、成長した今でもいちごが大好きで、毎日うどん鉢いっぱい食べるほどです。
そんな上村さんの思い出が詰まった、50,000パックに1パックのいちごは、まさに宝箱のようですね。

週1回でも月1回でも有機農産物を召し上がっていただく機会を増やしていただき、買い支えていただけると有機農家として有り難いなと思います。
何かひとつでもいいのでおいしい野菜をつくりたい。それは始めた頃から1mmもぶれていない。一生変わらないです。
現状に満足することなく、究極のおいしさを目指して有機農業を続ける上村さんの有機いちご、皆さんもぜひ食べてみてくださいね。

上村 慎二さん(かみむら農園)
2017年、八幡市で初めて有機JAS認証を取得。
土の力を活かした栽培方法を大切にしながら、環境にやさしい農業を広める活動にも力を入れています。
ビオ・マルシェの宅配は会員制のサービスです。ご購入ご希望の場合は、ご入会手続きページにて、会員登録をお願いします。
まずは試してみたい、資料も見てみたいという方は、お得なお試しセットもご用意しています。
もともと板前や営業職だった上村さん。
お義父様が育てた野菜を食べて感動し、「本当においしいものを作りたい!」という想いから有機農業の道を選びました。
いちごの有機栽培は、害虫や病気の影響を受けやすく、とても手間ひまがかかります。そのため、国内の有機いちご農家はわずか10名ほど。そのうちの一人が、上村さんです。